1989年に発売された森永製菓の「ICEBOX-アイスボックス」。グレープフルーツの風味がほんのりと感じられるこの氷菓は、従来のカップ入りかき氷とは一線を画す存在である。甘みを抑えた氷がカップにぎっしり詰まっており、一つ一つ手でつまんで食べても手がベトつかない。その手軽さ、カロリーの低さ(1個当たりわずか数カロリー)から、スナック感覚で食べられるという点が若者たちに支持された。
アイスボックスは青春の味
部活動後や学校帰りにコンビニエンスストアに寄り、このかちわり氷を買って仲間とシェアしながら食べた記憶がある人も多いだろう。価格も当時の100円という手頃さが学生の心を掴んだ。しかも、スプーンや木さじを使わず、片手でポリポリと食べられるというのは、現代のスマホ世代にも通じる魅力である。従来のかき氷とは違う軽い歯ごたえが、まさに「アイスボックス」の魅力を象徴していた。
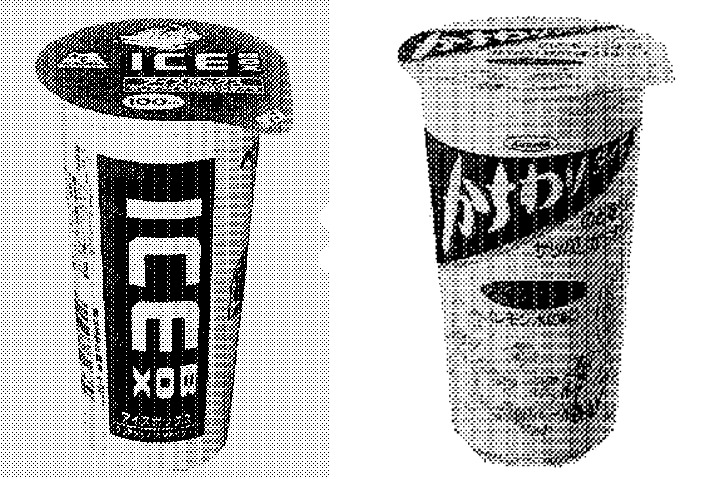
90年代にはライバルも続々と登場
そんな「アイスボックス」も、発売当初は他社との激しい競争を繰り広げていた。カネボウフーズの「アイスブリック」、明治乳業の「ロック&ロック」といったライバル商品が次々と登場したのである。実は、これらの味付け氷の開発の源流には、埼玉県行田市にある氷菓メーカー、トリー食品工業が存在する。トリー食品は1987年に味付け氷の製造技術を開発し、特許を出願していた。そして、森永製菓の「アイスボックス」は、この技術を取り入れた形で誕生したのだ。
かちわり氷戦争
しかし、この協力関係は後に裁判沙汰に発展する。トリー食品側は「苦労して開発した製造技術を盗まれた」と主張し、森永製菓側は「もともと当社が技術指導を行った商品であり、子会社での生産は独自の製法によるもので特許侵害ではない」と反論。こうして、大企業と独自技術を持つ下請け企業との間で“かちわり氷戦争”が勃発したのである。
この戦争がもたらした結果は、トリー食品の倒産だった。1994年、トリー食品は栃木県那須に新工場を建設し、生産力の強化を図った。しかし、借入金や経費増による資金繰りの悪化が進み、1998年には和議申請に至り、最終的に倒産してしまったのだ。
このエピソードから学べるのは、技術力や権利関係の重要性だけでなく、メーカーの立ち位置や役割がどれほど重要かということである。特に、商品開発に携わる企業や個人に対しては、深い敬意を払わなければならない。私たちが普段何気なく手にする商品にも、こうした背景があるのだ。歴史を知り、敬意を込めて味わうことで、商品そのものに対する感謝の気持ちが生まれるのではないだろうか。








